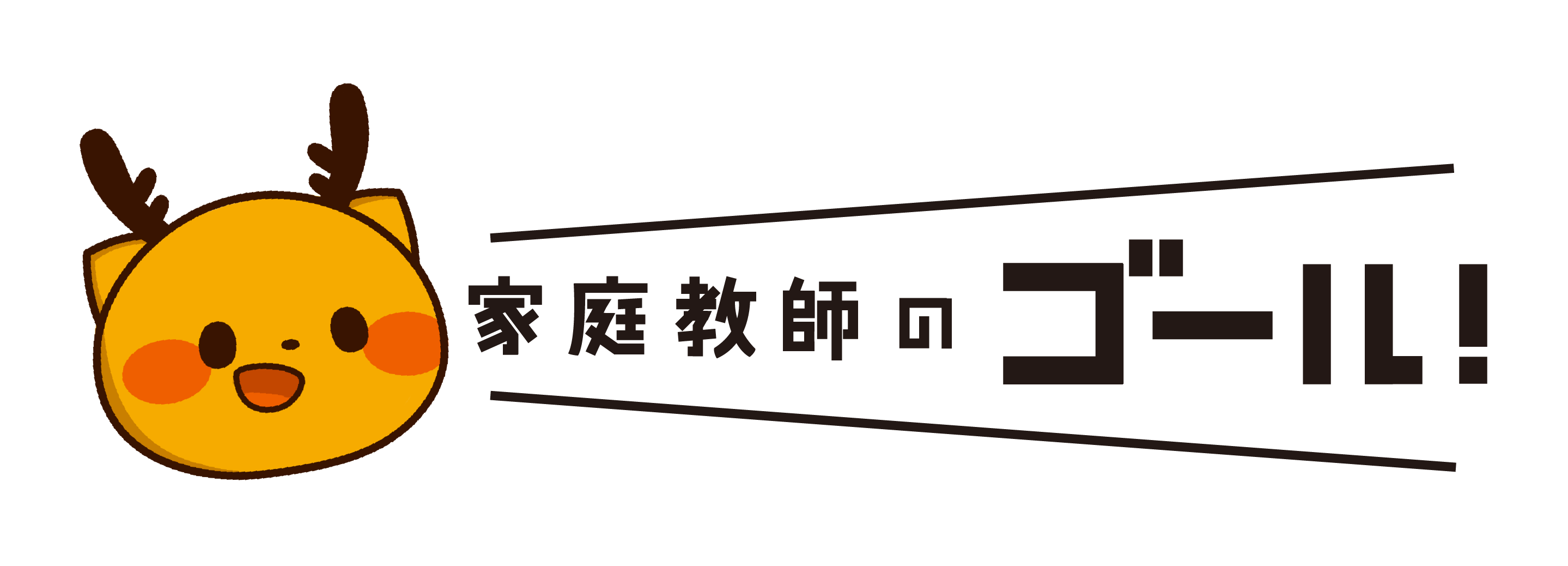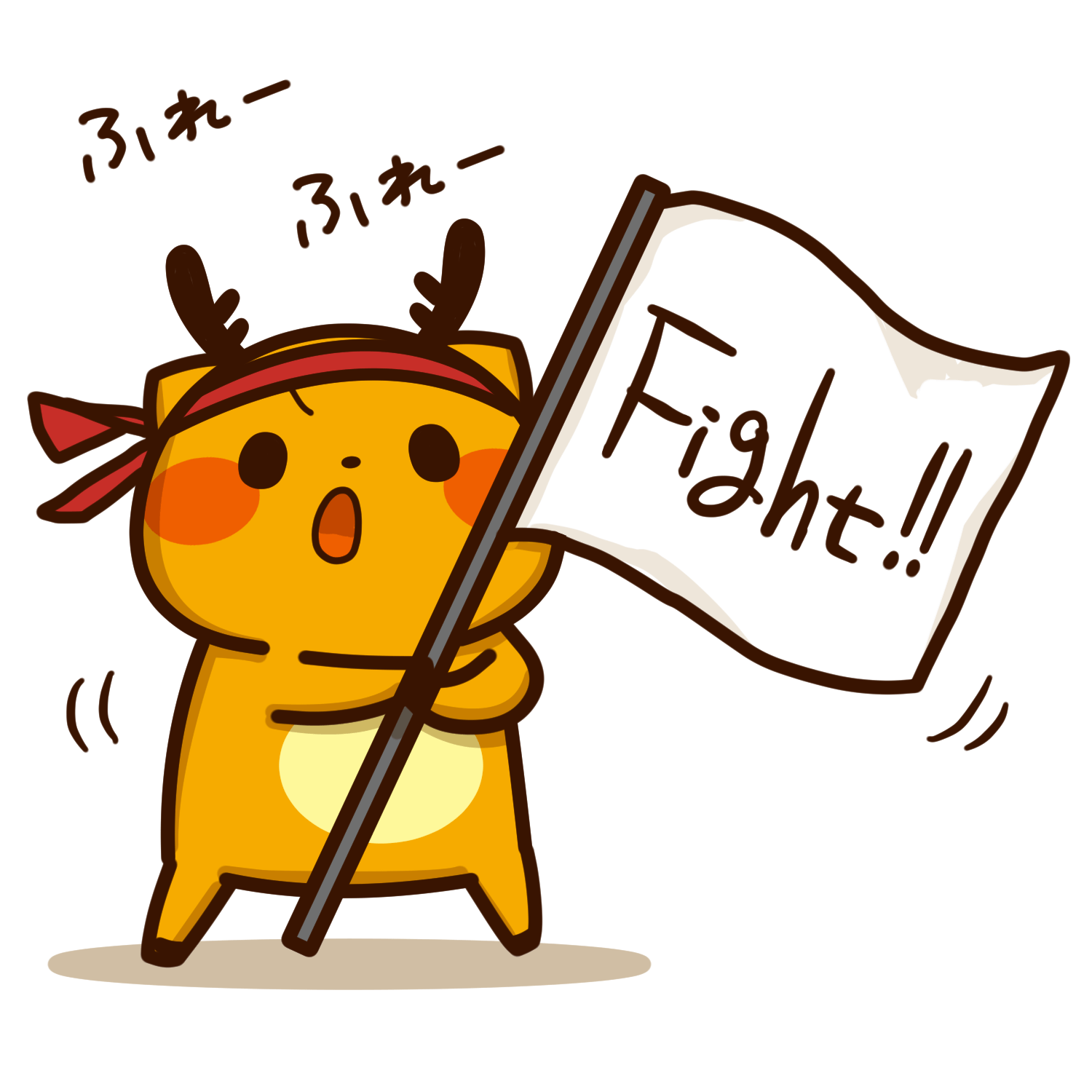〜化学変化の世界を楽しくマスターしよう〜
第1章:化学変化とは?
化学変化とは、ある物質がまったく別の物質に変わること。
たとえば「水」を分解すると、「水素」と「酸素」という全く別の物質に変わる。
これは目に見えない世界の不思議な変化で、科学の面白さの入口。
第2章:分解と化合
分解とは
1つの物質がいくつかの物質に分かれる反応のこと。
例:炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水・二酸化炭素に分かれる。
・分解の実験では「熱分解」という形でよく出題される。
・実験中は試験管の口を下げる(割れ防止のため)など、安全上のポイントも押さえておく。
化合とは
2つ以上の物質が合わさって、1つの新しい物質ができる反応。
例:水素と酸素が結びついて水ができる。
第3章:酸化と還元
酸化とは
物質が酸素と結びつく反応のこと。
例:鉄が酸素と結びついて酸化鉄(サビ)になる。
※燃焼(ものが燃える)は酸化の一種。
還元とは
酸素が物質から離れる反応のこと。
例:酸化銅が炭素と反応し、銅と二酸化炭素になる。
※酸化と還元はセットで起こることが多く、同時に理解しておくと得点しやすい。
第4章:質量の保存
化学変化の前と後で、物質全体の質量は変わらない。
これを「質量保存の法則」という。
例:鉄と酸素が反応して酸化鉄になったとき、
鉄の質量+酸素の質量=酸化鉄の質量、になる。
※ただし、反応中に発生した気体が逃げてしまうと質量が減ったように見えるので注意。
第5章:原子と分子
原子とは
これ以上分けられない、物質を作る最小の粒。
分子とは
原子がいくつか結びついてできた粒で、物質の性質を決める。
・原子は壊れない、なくならない、変化しない。
・分子の形が変わるのが「化学変化」。
第6章:単体と化合物
・単体:1種類の原子でできた物質(例:水素、酸素)
・化合物:2種類以上の原子でできた物質(例:水)
問題では「この中から単体を選べ」「化合物を選べ」という形式で出題されることが多い。
第7章:状態変化と温度
水を例にすると、以下のように状態が変化する。
-
氷(固体)
-
水(液体)
-
水蒸気(気体)
温度が上がると、個体 → 液体 → 気体へと変化していく。
この「状態の変化」も化学ではよく扱われる基本事項。
第8章:化学反応式の書き方
化学反応式では、反応の前と後で「原子の数」が同じになるように調整する必要がある。
例:
水素と酸素が反応して水になるとき
→ 2H₂ + O₂ → 2H₂O
このとき、両辺の水素原子と酸素原子の数が同じになるようにすることがポイント。
よく出る化学式や反応式はしっかり暗記しておく。
最後に:覚えやすいキーワードまとめ
| 用語 | 意味・覚え方 |
|---|---|
| 酸化 | 酸素とくっつく(酸素と「参加」) |
| 還元 | 酸素が離れる(酸素が「減る」) |
| 質量保存の法則 | 全体の重さは変わらない |
| 単体 | 1種類の原子だけでできている |
| 化合物 | 2種類以上の原子が合わさったもの |
このマニュアルを元に、暗記→実験→計算まで一気に仕上げて、1学期の理科テストでしっかり得点を取っていこう。
理解より「まず言葉を覚えること」からスタートしてOK!
講師や保護者の方もぜひ一緒にこのマニュアルを活用してください。